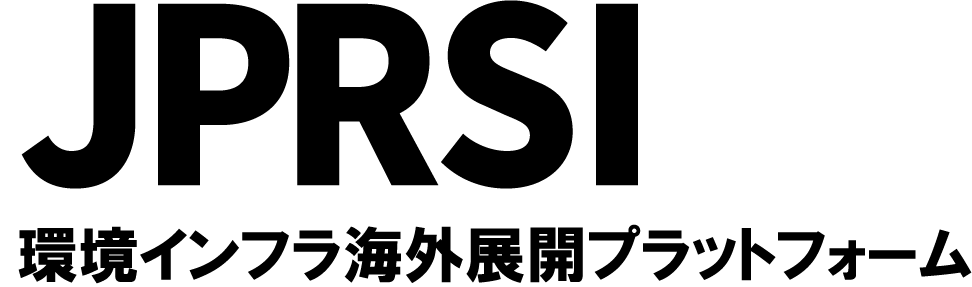現地の声:お伝えしたいこんな魅力
2025.8
バヌアツ
- 廃棄物・下水処理、震災復興に日本の環境技術需要 - ⅰ

知られざる太平洋の島国 バヌアツ共和国の概要
バヌアツ共和国は日本から約6,500キロ南東、太平洋上に浮かぶ島国です。13の大きな島と70以上の小さな島から構成されており、国土面積は新潟県と同じくらいの12,000平方キロですが、南北約1,200キロに及ぶ広大な国です。人口は約32万人であり、毎年2.5%程度増加し続けています。
日本からの直行便はありませんが、オーストラリア東岸から約1,800キロに位置していることから同国からなら航空便で約3時間程度あれば渡航可能な他、太平洋島しょ国の窓口となっているフィジー経由の渡航も便利です。世界で最も美しいビーチの一つと称されるサント島のシャンパンビーチや、歩行時間だけなら約30分で世界一火口に近づける活火山(ヤスール火山)等、自然の魅力にあふれている国です。
主たる産業は農業・観光業であり、バニラやコーヒーは日本にも輸入されています。また、島ごとに個性の異なるカカオを使用したチョコレートや現地のサトウキビを原料として生産されるラム酒も名産品となっています。観光の観点で見ても、伝統文化と長く統治していた英国・フランスの文化が共存する独特の空気を味わえるという点で世界の中で珍しい国の一つと言えるでしょう。
日本人が仕事や観光で渡航する機会の多い欧米やアジアではないため、その存在や現地の様子を知らないという読者の方も多いかもしれません。国際機関太平洋諸島センター(PIC)ⅱが本年公開したバヌアツの観光プロモーションビデオがありますのでこちらもご参照下さいⅲ。
 |
|---|
「裸族」の村落も存続している |
 |
|---|
ポートビラ中心部から車で40分程度の距離にある |
「太平洋の美しい島」が抱える社会課題
他方、『常夏の楽園』という印象とは裏腹に、バヌアツを含む太平洋に浮かぶ国々は地球上の環境問題を詰め込んだ、いわば「環境に関する課題先進国」です。筆者は現在PICからの業務委託も受けて、バヌアツを含む太平洋島しょ国14か国と日本の業務に取り組んでいます。本記事ではバヌアツで代表的な環境に関する課題をご紹介するとともに、直近で日本企業にビジネスチャンスが期待される背景をお伝えしたいと思います。
バヌアツが直面する環境に関する社会課題は3つ挙げられます。1つ目は電化率が非常に低く特に再生可能エネルギーを活用した発電普及率が低いこと、2つ目はごみ処理や下水処理能力が著しく低いこと、そして3つ目は2024年末に首都ポートビラ沖合を震源として発生した大地震後の復興が進んでいないことです。
バヌアツの電化率は約30%とされていますが、安定して電力が供給されているのは首都ポートビラと最大の島サント島の中心都市ルーガンビル等のみです。主要都市以外は系統に接続されておらず、離島・離村の電化率は約10%程度にとどまっていますⅳ。離島では大規模な発電所や、送配電設備の建設は採算性・土地の確保の都合上困難なため再生可能エネルギーの活用が欠かせません。バヌアツ政府は主要都市部以外でも電化率を高めるためにも2030年までに再生可能エネルギー利用の拡大目標を設定していますが、その進捗は芳しくありません。
また、飲食料品等を輸入に依存する経済構造となっている一方で、各種制約により進まない廃棄物処理も課題です。農地が少なく野菜が採れない、土地が狭く食品の加工工場が作れない、といった制約を抱えるバヌアツにおいて外国からの輸入品なしに生活は成り立ちません。その分ごみは溜まっていく一方。さらに、国土が狭く、ごみ処理場建設のための公的資金が不足している、ごみ収集の仕組みが機能していないといった事情からごみは国土の一部に山積みにされ、「廃棄物処理場」とは名ばかりの「廃棄物蓄積場」が少しずつ広がっているというのが実態です。
また、人口の増加や都市への人口集中に伴い、特に首都ポートビラでは住宅・オフィス街に面する湾の水質汚染が深刻化し、遊泳禁止令が発令されるまでに至っていますⅴ。“美しい海”を冠する島国に、泳げぬ湾が存在する――この事実が今、環境課題の輪郭をはっきり浮かび上がらせているといえます。
最後にバヌアツ特有の事情として2024年12月17日に首都沖合で発生した大地震による復興が進んでいないという点も重要ですⅵ。日本であれば震災が発生した後、一般的には数週間でライフラインが復旧し、2~3か月程度で損壊した建物が取り壊され、遅くとも半年後には復興に向けた再建工事が活発化する、という工程が一般的ですが、バヌアツでは政府庁舎等も移転を余儀なくされるほどの被害が発生したこともあり、なかなか復興が進んでいません。バヌアツにおいてGDPの約30%を占める観光業に重要なホテルも、震災発生から8か月たった今も首都ポートビラでの営業部屋数が通常の約半分程度との情報がありますⅶ。
日本企業の技術力が生きる
国や地域に影響する社会課題があれば、その解消策にビジネスチャンスが存在するのは国内外を問わず共通です。そして前項で列挙した課題の解消策は日本企業の得意分野ではないかと筆者は考えています。
例えば小規模な再生可能エネルギーの持続可能な活用法の導入。メガソーラーや大規模なバイオマス発電とは一線を画す、分散型電源の開発や蓄電技術を用いたオフグリッド電化技術には日本企業の参入余地があると言えます。具体的には、日本で現在実証実験・商用化が進められているスマートシティ関連、マイクログリッド関連の取組を現地事情に合わせて展開することで市場獲得が期待できるはずです。小規模ながら発電効率の良い発電設備を持つ企業、安定・安全な蓄電設備を持つ企業には、同一規格品の大量生産を前提とする価格競争ではなく、知恵と技術での勝負ができることもメリットの一つです。
例えば株式会社 東芝は2023年からバヌアツのマレクラ島等の離島で太陽光発電で充電したLEDランタンのレンタル、電気製品のシェアリングサービスを試行しています。本格的な事業展開間近であり、他の日本企業参入の先行事例として参考になるでしょうⅷ。
 |
|---|
2024年12月の大地震で損壊し、 |
 |
|---|
東芝がバヌアツで実施中のLEDランタンレンタル事業。 |
コンパクトかつ持続可能な廃棄物処理プラント、下水/汚泥処理技術を持つ企業は喫緊の課題となっている首都周辺の水質汚染、生活環境の悪化といった課題に貢献ができるため現地政府からも歓迎されます。この分野に関連した膜、ポンプ、配管、センサー、高分子凝集剤、浄化槽といった要素技術は日本企業が世界トップクラスを占めることは皆様ご存じの通り。公的セクターであるため、ODAスキームやJICA民間連携事業等の資金面の支援も検討に値します。これらを活用すれば、民間企業にとって新市場開拓の追い風となるはずです。(日本政府外務省の対バヌアツ開発協力方針に『都市部における廃棄物の適切な処理による周辺環境や公衆衛生の改善,沿岸漁業 資源の適切な管理のため,環境保全・管理(含:海洋プラスチックごみ対策)への支援に重点を置く』と明記されていますⅸ)
既にご説明した3つの課題のうち、廃棄物・下水処理についてはバヌアツに限らず太平洋島しょ国全般の共通の課題です。このため、バヌアツもしくは他の島しょ国において市場開拓に成功した企業は域内での「横展開」が可能となります。例えば同じ太平洋島しょ国の一つ、ツバルでもごみの堆積は代表的社会課題の一つ。2024年12月、PICがツバルに国際協力系YouTuberの原貫太氏を派遣し、現地の最新の状況と課題を整理する動画が公開されていますので是非ご覧くださいⅹ。
バヌアツの首都ポートビラにとって特に重要なのは2024年12月に発生した大地震被害からの復興です。現時点ではまだ地震で倒壊した建物のがれき除去、および倒壊の危険性がある建物の取り壊しが順次進められている状況です。他方、遠からず首都市内の住居、商業ビル、ホテル等の建て直し需要が盛り上がることは「既に起こった未来」と言えます。
Build Back Betterという言葉があるように今回地震で倒壊したビルの建直しにあたっては耐震性に優れ、エネルギー効率のよい日本の技術を用いた建築技法への関心が高いと言えます。過去バヌアツでは歴史的経緯からフランスを中心とした欧州系企業あるいは中国系企業が建築したビルが多く存在していました。しかしながら、今般の地震を経て、人々がビル建設の質、特に「耐震」の重要性に気付いていることは現地からひしひしと伝わってきますⅺ。
確実に存在する復興需要を追い風としてより安全な建物、より環境に配慮した(ライフタイムコストの低い)建築技術をアピールすることができれば、日本企業がバヌアツで市場開拓できる可能性は高いと言えるのではないでしょうか。この点でネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)に関連する技術を持つ企業あるいは建設会社の参入は今がチャンスです。
|
執筆者紹介 株式会社海外安全管理本部 プロフィール |
|---|
マクロ情報:バヌアツ (2019年)
| GDP(百万米ドル) | 1 |
|---|---|
| 人口(百万人) | 3187 |
| 1人あたりGDP | 0.3 |
- 本資料はJPRSIが信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性・確実性を保証するものではありません。
- 本資料に従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するもので、JPRSIは何らの責任を負うものではありません。
- 本資料へのリンクは自由です。それ以外の方法で本資料の一部または全部を引用する場合は、出典として「JPRSI(環境インフラ海外展開プラットフォーム)ウェブサイト」と明示してください。
ⅰ 冒頭写真: バヌアツのタンナ島に位置するヤスール火山は活火山火口を間近に観察できる観光地
ⅱ https://pic.or.jp/
PICは日本と太平洋島しょ国の経済交流(投資・貿易・観光)を促進するために設立された国際機関。日本政府、太平洋の14か国に加えオーストラリアとニュージーランドが共同拠出しており、バヌアツを含む太平洋島しょ国への事業進出に関する情報が集積している日本国内唯一の機関と言える。国際機関であるがゆえにコンサルティング・フィー等は必要ない。、環境関連ビジネスで太平洋島しょ国への進出を検討される際には一度コンタクトをとられてみることを推奨。
ⅲ https://www.youtube.com/watch?v=wc41vRIxK7o
ⅳ https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12288627.pdf
ⅴ 参考:バヌアツ地元メディア報道
https://vbtc.vu/government-may-extend-lagoon-use-ban-as-water-tests-confirm-high-bacterial-levels/
ⅵ https://www.abc.net.au/news/2025-05-08/port-vila-earthquake-recovery-tourism/105260536
ⅶ 現地でホテルを経営する日本人からの聞き取り
ⅷ https://www.toshiba-clip.com/detail/p=10563
ⅸ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072632.pdf
ⅹ https://www.youtube.com/watch?v=Qrv0aVUUCyY
ⅺ https://www.abc.net.au/pacific/programs/pacificbeat/van-buildings-quake/105080078