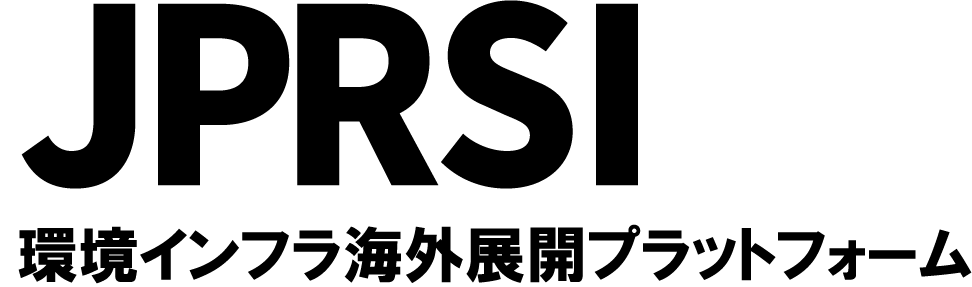現地の声:環境省駐在員からの
耳寄り情報
2025.8
インド
Viksit Bharat 2047(2047年までに先進国へ)
- 環境ビジネスの商機は -

1.冒頭
インドで環境ビジネスが花開くチャンスはあるのか、あるとすれば有望な分野は何なのか、インドに赴任して3年近く、これらの質問を自分に問いかけてきました。環境保全の志向が高いのか低いのか、その両方とも取れるような状況がインドでは渾然一体としているように思えました。一方では、デリーのテイクアウトの外食チェーン店で配布するスプーンやフォークは木製で、プラスチック製のものは全くと言ってよいほど見かけませんし、スーパーのレジで提供される袋は不織布で、プラスチック製ではありません。そしてデリーの道を行き交うトラック等の小型・中型の作業用車両、また殆ど全てのオートリクシャーiは、SO2(二酸化硫黄)を排出しないCNG(圧縮天然ガス)車です。しかしながら他方で、環境保全施策の後退と思えるような報道や出来事にも接してきました。こうした状況の中、インドの国全体として、開発を進めるダイナミズムのようなものも肌で感じることができましたし、それを体現しているのが、モディ首相が打ち出した、独立後100年となる2047年までに完全な先進国になるとのビジョンである“Viksit Bharat 2047”であり、このビジョンがインドでの環境関連ビジネスにも少なからず影響を及ぼすと考えるに至りました。
 |
|---|
デリーのリクシャーはCNG車 |
2.大気汚染対策:石炭火力発電所における脱硫装置の設置義務緩和
まず大気汚染対策関連で私が驚いたニュースをご紹介します。環境・森林・気候変動省は、180基ある石炭火力発電所における脱硫装置の設置期限をこれまで数回にわたり延長した挙げ句、2025年7月に、デリー及び100万人以上の都市から10km圏内に所在する石炭火力発電に関しては、脱硫装置の設置期限を2027年まで延長しつつ、設置義務自体は残したものの、大気汚染が深刻な都市から10km圏内の場合は専門家の判断次第で設置してもしなくてもどちらでもよいとし、それ以外については設置義務を無くした、という報道がありました。割合で見ると、脱硫装置の設置義務が完全に無くなった石炭火力発電所は実に78%を占めます。
では、インドの大気汚染の実態はどうでしょうか。スイスのIQAirが発表した2024年のWorld Air Quality Reportによると、インドは世界で5番目に大気汚染が深刻な国で、世界で最も汚染された都市の上位20位のうち13都市がインドにあり、デリーは世界で最も汚染された首都という結果でした。こうした現状と相まって、インドの環境保護系の研究機関は、脱硫装置の設置義務を無くしたり延期する環境・森林・気候変動省の動きを批判的に見ています。しかしながら、一般のメディアの中には、インド政府は現実的で経済的に健全かつ環境に配慮したバランスの取れた持続可能な開発モデルへのコミットメントを再確認した、と評価した報道もありました。
3.ごみゼロ都市に向けた挑戦
次にごみ問題に触れます。インドには、モディ首相の提唱で始まった「クリーン・インディアミッション」という計画があります。第一期は2014年に開始し、2019年までに野外排泄を撲滅することを目的とし、成功裏に計画期間を終了したとされています。その後、2021年には第二期の取組が、ごみゼロ都市をスローガンとして開始しました。第二期の取組期間は2026年までとされていますが、担当する住宅都市省や水活用省にはクリーン・インディアミッション第三期担当課長という役職の職員が存在しているため、次期計画の策定も平行して進め、息の長い取組が継続すると考えられます。
しかしながら、インドを旅して残念に思うのは、大都市から小規模都市まで共通して多量のプラスチックごみが街中や河川に放置・投棄されていることです。
その中で、明るい兆しは2025年2月のデリー準州議会選挙で国政の政権党であるBJPが勝利した頃から、デリーに4箇所ある廃棄物発電所全てに新たな焼却炉を設置する等の拡張計画が順調に進んでいるらしいことです。新聞報道で、デリー準州首相に対してこれらの拡張計画の説明がなされたという記事も目にしました。これらの計画に対して、電力の買取価格がどの程度、他の再エネに比較して高額に設定されるのか、また、焼却施設の建設に対する中央政府の補助金が出るかということに対して一部メディアは関心を持っているようです。デリーでの取組が成功すれば、他の都市でのごみゼロの取組みも加速化することが期待されます。
 |
|---|
デリーのBhalswa廃棄物埋立地。廃棄物が約60mにまで積み上がっている。 |
4.河川の汚染状況と対策
次は河川の汚染に関してです。インドの環境問題や政府の環境対策をウォッチするCSE(The Center for Science and Environment)という団体は、年次報告書を毎年出版してインドの環境問題の実情をレポートしています。2025年度版の報告書では、環境・森林・気候変動省が擁する規制部局である中央公害管理局(CPCB)は、全国の河川に計870箇所の水質モニタリング地点を設けているが、そのうち37%でしか適切な測定が行われていないらしいこと、また、測定される半数の河川で、ヒ素・カドミウム・クロミウム・銅・鉛・水銀・ニッケル等の重金属が高濃度で検出されていることを報告しています。デリー市内を流れるヤムナ川はガンジス川の支流であり、ヒンドゥー教徒の信仰の対象でもありますが、生活排水・工業排水を原因とする多量の泡で水面が覆われてしまうこともあります。浄化対策を担うのは、BOD(生物化学的酸素要求量)など生活環境項目の測定も行うCPCBに加え、下水道や浄化槽の整備も進める住宅都市省です。住宅都市省は前述のクリーン・インディアミッションに基づき河川の浄化施策も推進していますし、JICA協力によりデリー市内にはインド最大規模とされるオクラ下水処理場も建設されましたので、汚染が改善することが期待されます。
5.エネルギー自給化に向けて
最後にエネルギー問題について見ていきます。インドは中国、米国に次ぐ世界第3位のエネルギー消費国で、9割を化石燃料に依存しています。またインドの公的なシンクタンクであるNITI Aayogによれば、2022年時点でインドが消費する原油の約9割、天然ガスの約6割、石炭の約3割は、輸入に依存しています。また、急速な経済発展を支えるため、2031年度までに80GWの石炭火力発電所を増設する計画を発表しており、エネルギーを取り巻く状況には厳しいものがあります。そのため、インドは再エネにも注力しており、インドの温室効果ガス排出削減目標であるNDC(2025年7月時点で2030年NDCが最新)においては、2030年までに再エネ起源エネルギー(電源構成)を50%とする目標を掲げ、この目標の下、太陽光・風力・バイオマスなどの再エネ電源の開発を進めています。とりわけ注目が集まっていると感じるのは、牛糞やサトウキビの絞りかす、その他の生ごみからCBG(圧縮バイオメタンガス)を製造する事業で、一部の日本企業も既に参入しています。冒頭に記載したようにインドのモビリティーには既に多くのCNG車両が投入されていますので、生ごみ等からCBGを生産して車両の燃料に混入する形で使用できれば、インド政府が目指すエネルギー自給化に貢献します。この取組は、石油省が自動車用CNG燃料及び都市ガスへのCBG混入を義務化したことにより、一気に加速化しています。また、JCM(二国間クレジット制度)については、インド国内で2026年に稼働すると言われるカーボンマーケットの整備と相まって、今後、最も有望な分野であると感じます。グリーン水素やグリーンアンモニア、グリーン鉄鋼などは、とりわけインド側のニーズや注目度が高い分野と言えます。今般日印政府がJCMに合意したことで、両国にとって大きなメリットのあるプロジェクトを実際に開始できるようになったことはとても意義深いことだと思います。
 |
|---|
カルナータカ州で見かけた風力発電。写真に収まっているだけで14~15基を数える。 |
 |
|---|
タクシーのトランクを開けるとCNGガスタンクがあることがインドでは珍しくない。 |
6.結語
インドは、独立から100年後となる2047年までに先進国となる目標に向かって邁進しています。国民の経済的な格差が大きいことから課題は山積し、現在は製造業の振興やそれを支える電力の確保に専念し、政府・企業を問わず、良好な環境を保つために資金を投じるには時期尚早という意識が強いように思えます。この状況の中、日本側からインド側へ提案を行う際には、気候変動対策や環境保全の重要性のみを言うのではなく、コスト削減や資金確保の観点から、インド政府やインド企業が納得感を持って受けとめるような提案をすることが、少なくとも近い将来においてはインドで成功するための重要なポイントであると感じます。
 |
|---|
|
執筆者紹介 環境省 地球環境局国際連携課 2022年8月にインドのニューデリーに赴任し、在インド日本国大使館の経済班にて環境アタッシェとして3年間勤務。 |
|---|
マクロ情報:インド (2023年)
| GDP(百万米ドル) | 3,638,490 |
|---|---|
| 人口(百万人) | 1,429 |
| 1人あたりGDP | 2,547 |
- 本資料はJPRSIが信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性・確実性を保証するものではありません。
- 本資料に従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するもので、JPRSIは何らの責任を負うものではありません。
- 本資料へのリンクは自由です。それ以外の方法で本資料の一部または全部を引用する場合は、出典として「JPRSI(環境インフラ海外展開プラットフォーム)ウェブサイト」と明示してください。
ⅰ 三輪タクシー。auto-rickshaw