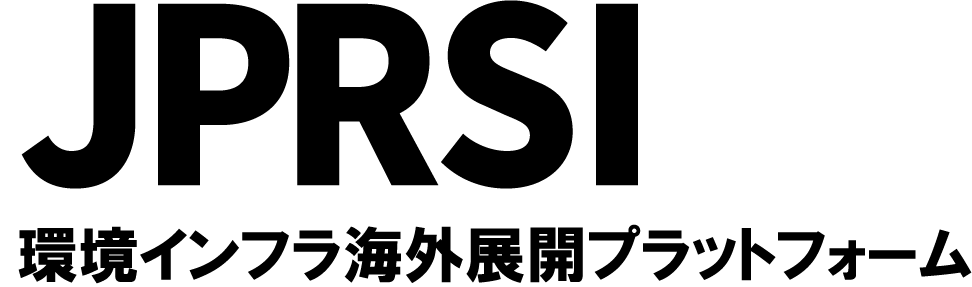現地の声:お伝えしたいこんな魅力
2025.10
【シリーズ】バングラデシュ
課題大国はビジネスチャンスの宝庫となるか?
「気候変動フロンティア」へようこそi

デルタの国のパラドクス
「バングラデシュ」と聞いて、皆さんどんなイメージをお持ちだろうか。「留学生」、「近所のコンビニにいた店員さん」、「洪水」、途上国ビジネスに詳しい方なら、「マザーハウスⅱ」、「ユーグレナⅲ」、「ムハマド・ユヌス博士とマイクロファイナンス が生まれた国ⅳ」、「世界のアパレル産業の集積地ⅴ」あたりだろうか。
どれも正しい。だが私は敢えてお伝えしたい。「気候変動の課題大国バングラデシュこそ、ビジネスチャンスの宝庫である」と。
筆者は2006年以来、JICAの専門家などとしてこの国と関わり続けている。自分たちへの利益誘導しか興味がないような政治家や役人もいるが、庶民は、特に女性は驚くほど働き者だ。男たちがお茶屋でクダを巻いている間に、彼女たちはせっせと、畑仕事から家事から老いた親と子どもと家畜の世話を、電気も水道もロクにない中で全部やっている(ちなみに田舎ではいまだに牛糞を乾かしたものを煮炊きに使っている)。彼女たちの明日が少しでも良くなるために何かできないか。そう思わせる引力が、この国にはある。
一言でいえば「世話は焼けるが愛嬌ある友人の面倒をつい見てしまう」心境に近い 。本連載では、この国の環境・気候変動問題が、いかにして世界のビジネスにとって魅力的なフロンティアとなりうるのかを解説していく。
かつて「貧困国の象徴」だったバングラデシュ。北海道と東北を合わせたほどの国土の多くが海抜10m以下の低デルタ地帯に、日本の人口の1.4倍である約1.7億人が暮らす。Global Climate Risk Index 2021で世界7位にランクしたことがあり、世界銀行(2022)ⅵの分析によれば、深刻な洪水が発生した際には最大でGDPの9%が失われかねないという巨大なリスクを常に抱えている。しかしそのような厳しい現実を背景にしながらも、アジア屈指の活力を秘めた国でもある。2000年代以降、縫製業をエンジンに力強い経済成長を実現してきた。世界経済の減速を受け、成長率は2025年度に3.8%まで落ち込んだが、国際通貨基金(IMF)は2026年度には5.4%まで回復すると予測している。この「深刻な脆弱性」と、それでもなお未来への成長を目指す「ダイナミズム」のパラドックスこそ、バングラデシュの今を読み解く鍵なのだ。
 |
|---|
ダッカ市内のカフェに集う人々 |
国家百年戦略「デルタプラン2100」とNAP、ふたつの国家計画
この国の未来を語る上で欠かせないのが、二つの壮大な国家計画だ 。一つは2100年までを見据えた国家百年戦略「バングラデシュ・デルタプラン2100(BDP2100)」 。これはオランダの知見を取り入れ、水資源管理や経済成長などを統合した野心的なマスタープランだ 。もう一つが、2022年に国連に提出された「国別適応計画(National Adaptation Plan: NAP)」であり、2050年までの113の優先プロジェクトを特定している 。問題はそのコストだ。BDP2100の第1期に約370億ドル、NAPの実現に約2,300億ドルが必要と試算される。この莫大な金額は国家予算をはるかに超える規模であり、公的資金だけでは到底賄いきれない。この巨大な資金ギャップを埋める鍵こそが、民間セクターの資金と技術なのである (なおBDP2100は、保守的な見積もりでも毎年GDP比2.5%相当の投資が必要で、うち0.5%は民間投資から、としている)。
なぜ今、あえて世界はバングラデシュに注目するのか
「汚職やインフラの脆弱性、独特のビジネス慣習など、リスクが高すぎる」――多くのビジネスパーソンがそう考えるのはもっともだ 。私自身、この国で何度も煮え湯を飲まされた(最たるものは、1年以上かけて関係者と協議してきた円借款の内容を、セクター構造改革は骨抜きにしてインフラ建設部分だけに限定しろと、協議最終局面でバングラデシュ政府からちゃぶ台返しを喰らった事案である)。その懸念はもっともだと痛感している。
しかし、そのリスクを織り込んだ上でなお、世界銀行やJICAといった国際パートナーたちが巨額の資金を投じ、その先に民間投資の可能性を見続けるのには理由がある。
第一に「気候変動のリアルな実験場」としての重要性だ 。この最前線で成功する適応策は、世界のモデルとなりうる。第二に「巨大な課題解決型市場」としての魅力である 。約1.7億人の人口を抱え、後発開発途上国(LDC)卒業も間近な国の成長力。インフラの脆弱性と人口の多さは、裏を返せばエネルギー、交通、廃棄物管理、災害情報といった分野での巨大なビジネスチャンスを意味する。第一と第二の理由の掛け算こそが、冒頭の「気候変動の課題大国バングラデシュこそ、ビジネスチャンスの宝庫である」と筆者が考える理由である。何せ「市場」は、気候変動のチャレンジが汲んでも尽きぬ泉のように満載の地なのだ。加えて舞台裏を明かせば、筆者を含め日本政府関係者はバングラデシュの省庁や法律規制、各種国家計画の状況には通じているものの、具体的なビジネスに関する嗅覚は、悲しいかな「極めて限定的」である。世界最弱のパスポートでも、めげずに世界中に出稼ぎに行くバングラデシュ人の逞しさと商売っ気を、筆者のような行政側の人間では到底活かしきれない。この国で、持続可能な形で真剣に儲けたいというビジネス側の方々が必須なのだ。
 |
|---|
ハオール地方の農民一家。 |
そして第三が「地政学的な要衝」としての顔だ 。日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」構想において、東南アジアと南アジアの結節点に位置するベンガル湾地域が極めて重要な位置を占めることは論を俟たない。日本が主導する「ベンガル湾産業成長地帯(BIG-B)」構想などが、既製服(RMG)産業に偏りがちだった経済構造の多角化を後押ししている 。気候変動関連のビジネスチャンスとしては、JICAが現在実施中のモヘシュカリ・マタバリ統合的インフラ開発イニシアティブ(MIDI)を起点に、今後巨大な物流の変化や、それに伴うサービス(気象予報やBCPなど)のニーズもあるかもしれない。
 |
|---|
マタバリ港開発候補地周辺エリアの様子。 |
もちろん、リスクは存在する。信頼できる現地パートナーとの連携が成功の鍵を握る 。もちろん、行政の非効率さや独特のビジネス慣習がすぐになくなるわけではない。だからこそ、リスクヘッジの「戦略」が不可欠だ。幸い、この国にはBRACⅶをはじめとする高いレベルのNGO(という名の実質的には巨大コングロマリット)や、海外ビジネスに精通した人材が育ってきている。信頼できる現地パートナーを見つけることが、この複雑な市場を航海するための最も有効な羅針盤となる。
次なるフロンティアへの招待
バングラデシュは、独立運動ⅷの引き金の一つがサイクロン被害への政府の対応の遅れだったという歴史を持つ、災害と共に生まれ、生きてきた国だ。しかし、彼らは決して悲観していない。この国はマイクロファイナンスなど逆境からイノベーションを生み出してきた。そして建国の父ムジブル・ラーマンが日本の国旗に範をとったという説もあるほど、大の親日国である。それは当地で奮闘される日本企業やJICAに寄せられる信頼からも、日々伝わってくる。課題が山積みだからこそ、面白い。未完成だからこそ、自分たちの手で未来を創るダイナミズムがある。バングラデシュはもはや単なる援助の対象国ではなく、課題解決という名のビジネスチャンスが眠る「次なるフロンティア」なのだ。この記事を読んで、「うちの技術で何かできるかもしれない」と感じていただけたなら幸いだ 。
次回は、この国の喫緊の課題であり、ビジネスチャンスの宝庫でもある「気候変動(緩和)」の最前線について、より深く掘り下げていく。
 |
|---|
|
執筆者紹介 JICA専門家(開発・気候変動レジリエンス政策アドバイザー) 米国会計系コンサルティング会社勤務後、2006年より旧国際協力銀行(JBIC)にて勤務。JICAケニア事務所、JICAバングラデシュ事務所、JICAコンサルタント、環境省地球環境局等を経て、2024年12月より現職。 |
|---|
マクロ情報:バングラデシュ (2022年)
| GDP(百万米ドル) | 460,201 |
|---|---|
| 人口(百万人) | 169 |
| 1人あたりGDP | 2,731 |
- 本資料はJPRSIが信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性・確実性を保証するものではありません。
- 本資料に従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するもので、JPRSIは何らの責任を負うものではありません。
- 本資料へのリンクは自由です。それ以外の方法で本資料の一部または全部を引用する場合は、出典として「JPRSI(環境インフラ海外展開プラットフォーム)ウェブサイト」と明示してください。
ⅰ 冒頭写真:ハオール地方の川で洗濯する女性。筆者提供(以下、注のない写真はすべて同様)
ⅱ マザーハウス https://www.motherhouse.co.jp/pages/about
ⅲ ユーグレナGENKIプログラム https://www.euglena.jp/genki
ⅳ 参考:ノーベル平和賞を受賞したグラミン銀行を支えた日本のODA
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/annai/pdfs/g_bank_1.pdf
ⅴ 参考:「世界の縫製工場バングラデシュ 労働集約型生産拠点としての実力を探る」
みずほ総合研究所(現 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)作成 2013年7月発行
https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/mhri/research/pdf/insight/as130724.pdf
ⅵ 世界銀行グループ 2022年: Bangladesh Country Climate and Development Report
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/1d6b85c3-4959-5f93-af88-dda33f52ee37
ⅶ BRAC https://www.brac.net
ⅷ 参考:NHK「映像の世紀バタフライエフェクト」 https://www.nhk.jp/p/butterfly/ts/9N81M92LXV/episode/te/R1VJ85L4QN/